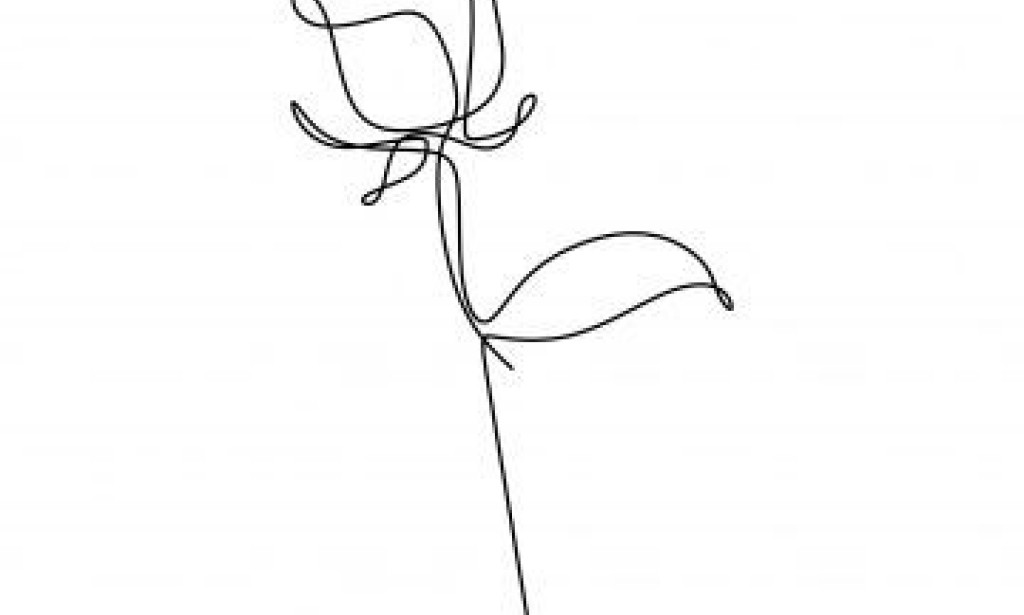
ロアルド・ダール
ロアルド・ダール
そろそろ六時になろうかという時刻だったので、ビールでも買って、プールサイドのデッキチェアに寝そべり、しばらく夕日を眺めたらどうだろう、と考えた。
バーで買ったビールをさげて外へ出ると、プール目指して庭をぶらぶら歩いていく。
見事な庭の芝は手入れが行き届き、ツツジの植え込みや背の高い椰子の木が続いた。椰子のてっぺんでは強い風にあおられた葉が、シューッ、パチパチ、と火でもついたようにざわめいている。茶色い大きな実が固まって葉陰にぶらさがっているのが見えた。
プールサイドにはデッキチェアがずいぶんあり、白いテーブル、明るい色の大きなパラソルとともに、よく日焼けした水着姿の男や女が腰を下ろしている姿が見えた。プールの中では三、四人の娘と十数人の若い男が水をはねかしながら、大声をあげては大きなゴムのボールを投げ合っている。
しばらく立ったままそれを眺めた。娘たちはホテルに滞在しているイギリス人らしい。若い男のほうは見たことがなかったが、聞こえてくるアメリカふうの発音から、おそらく今朝入港したアメリカ海軍の練習艦の士官候補生ではないかとあたりをつけた。
黄色い日傘の下、椅子が四つとも空いている卓まで歩いて腰をおろすと、コップにビールを注いで、タバコをくわえたまま、背もたれに身をゆっくりとあずける。
夕日を受けて、ビールとタバコを手に長々と座っているのは、たいそう気持ちの良いものだった。薄緑色の水のなかでしぶきをあげている人々をここから眺めるのも悪くない。
アメリカの水兵たちは、イギリス娘とうまくやっているようだった。水に潜って女の子たちの足をすくって倒してもかまわないほどの仲にはなっているらしい。
そのとき、小柄な初老の男がプールサイドをきびきびと歩いてくるのが目に留まった。染み一つない真っ白いスーツに身を包んで、一足ごとにつま先立ちになるような軽く弾む歩調で、足早にこちらに向かってくる。大きなクリーム色のパナマ帽をかぶって、人々や椅子に眼をやりながら、男はせかせかとやってきた。
私のそばまで来ると足を止めた男は、にっと笑って上下の歯、小ぶりで微かに黄ばんで不揃いな歯並びを見せた。私も笑い返す。
「失礼いたしますですが、ここ、腰掛けてよろしゅございますか」
「もちろんです。どうぞ」
男は椅子の後ろへひょこひょこと回り込むと、だいじょうぶかどうか確かめてから、腰掛けて足を組んだ。白いバックスキンの靴には、一面に換気用の小さな孔が空いている。
「よい日暮れですね。ジャマイカの夕方、いつも美しい」 男のアクセントがイタリア系のものか、それともスペイン系なのか、はっきりとはわからなかったけれど、南米のどこかであることにはまちがいなさそうだ。しかも、近くで見れば、思ったよりも歳が上だということもわかった。六十八歳から七十歳というあたりだろうか。
「そうですね。ここはいいところだ」
「あの、あちらにいる方々、どのような方とお聞きしてもかまいませんですか。ホテルの人、ありませんですね」そう言いって、プールにいる連中を指さした。
「おそらくアメリカの水兵だと思いますよ。海軍で訓練中のアメリカ人でしょう」
「そうですね、あの人たち、アメリカ人、まちがいない。あのように大騒ぎする人々、ほか、ないです。あなた、アメリカ人、ないですね?」
「そうです。私はアメリカ人ではありません」
そのとき急に、そのアメリカ人士官候補生のひとりが私たちの前にやってきた。全身から水がしたたり、イギリス娘を連れている。
「ここ、ふさがってます?」
「空いてますよ」わたしは答える。
「座ってもいいですか」
「どうぞ」
「どうもありがとう」
若い男は腰をおろすと、手にしていたタオルを開いて、タバコとライターを取りだした。娘にタバコを差し出したが、断られる。私にもすすめたので、受け取った。小柄な老人は言った。
「ありがとう。でもいらないです。私、私のタバコ、ありますです」ワニ皮のケースから葉巻を一本抜き取ると、小型のハサミがついたナイフを取り出して、葉巻の端を切った。
「火を使ってください」アメリカ人青年が自分のライターを差し出す。
「風、あるから、ダメですね」
「大丈夫。どんなときだろうがつくライターなんですから」
小柄な老人は、火のついていない葉巻を口から離すと、小首を傾げて青年をじっと見た。
「いつだって、かならず、つくですか」とそっと聞いた。
「ええ、これまで一度だってつかなかったことがないんです。ともかく、ぼくがやった限りではね」
老人はなおも首を傾げたまま、青年に目を据えたまま聞いた。「ほほう。というと、これが失敗することがないので有名なライターなのですか。そうあなたは言いますね?」
「そう」青年は答えた。「そのとおりです」
十九か二十といった年格好、そばかすの散った面長な顔立ちで、こころもち尖った、小鳥の嘴を思わせるような鼻をしている。胸はまださほど日に焼けておらず、そこにもそばかすがあって、赤みがかった胸毛がうっすらと生えていた。右手にライターを持ち、いまにもやすりをまわそうと待ちかまえている。
「失敗なんてありえない」たいしたことじゃないんだけど、わざと大げさに言ってるんだよ、とばかりに、にんまりと笑ってみせた。「請け合いますよ、これは絶対に火がつくライターなんです」
「チョト待てください」
葉巻を持ったままの手を高くあげて、車を停めようとするように手のひらを相手に向ける。「待てくださいです」その声は奇妙なくらい穏やかで抑揚がなかった。相変わらず青年から片時も目を離そうとしない。
「私たち、チョトした賭けができますと思いませんか」そう言って青年に笑いかける。「そのライター、つく、つかない、私たち、賭けることできますですね」
「もちろん賭けならいくらでもできますよ。やります?」
「あなた、賭け、好きですね」
「ええ、しょっちゅうやってます」
老人は口をつぐんだまま、葉巻をためすすがめつしていたが、その様子はあまり好ましいものではなかった。老人にはすでに何かしらの思惑があって、それは青年をなぶるためのものであるように思え、同時に老人には何かしらうかがいしれぬ秘密があって、それを舌なめずりしながら味わっているようにも思えたのである。
青年に眼を戻すと、ねっとりと聞いた。「私も賭け、好きですよ。私たち、ライター使っておもしろい賭け、できますですね。おもしろい、賭け、ね?」
「おっと、ちょっと待ってください」青年が言った。「そんなことはできないな。ぼくに賭けられるのは1ドルか、ううん、ここだといくらなんだろう――何シリングとか」
老人はまた手をひらひらさせた。「あなた、わたしの言うこと聞きますね。これから私たち、楽しいことします。私たち、賭け、やるです。私たち、ホテルの私の部屋、行くですね。そこは風、ないですし、私、あなたがこのすばらしいライター、一回も失敗なしで十回連続、火、つけられる、失敗するに賭けますね」
「十回連続ぐらい、わけないですよ」
「わかりました。よろしいです。私たち、賭けるですね?」
「よしきた。1ドル賭けるよ」
「違うですよ。私、あなたともっと楽しい賭けするです。私、お金持ち、それに賭け事、大好きです。私の言うこと、聞くですね。ホテルの外、私の車あるです。とても良い車。あなたのお国から来たアメリカの車。キャデラック……」
「うわぁ、えらいことになったな」青年はデッキチェアに身をあずけて笑い出した。「ぼく、そんなたいそうなもの持ってないですよ。そんなバカみたいなこと、できないよ」
「全然バカみたい、ないです。あなた、ライター、連続十回火をつけます。うまくいったらキャデラック、あなたのもの。あなた、キャデラック、持ちたいですね、そうでしょう?」
「そりゃもちろん。キャデラックはほしいけどさ」青年はまだニヤニヤと笑っていた。
「よろしい。結構です。わたしたち、賭け、やります。私、私のキャデラック賭けるです」
「で、ぼくは何を賭けるんです?」
小柄な老人は、未だに火のついていない葉巻から、赤いシガーバンドを慎重にはがしている。「私、できないこと、お願いしません、親友。わかりますね」
「だから何を賭けろと?」
「あなた、とても簡単ですよ」
「結構。そりゃ手間が省けるね」
「ほんのチョトしたもの、あなた、くれること簡単。おまけに、もしなくなっても、そんなに困らない。いいですね?」
「だから何なんです」
「何か、いうと、たぶん、あなたの左手の小指とか」
「なんだって!」青年の笑いはすっと引っ込んだ。
「そうです。どうですか? あなた勝つ、車、あなたのもの。あなた負ける、私、指もらう」
「わからないな。どういうことなんです、指をもらうって」
「私、切るです」
「なんてことを! とんでもない話だぜ。1ドル賭けりゃ十分だよ」
老人はふんぞりかえると両の手のひらを上に向けて広げ、さげすんだように肩をすくめてみせた。「結構、結構。私、わかりません。あなた、火がつく、言いますね、でも、賭け、しない。なら、私たち、忘れましょう。いいですね?」
青年は腰をおろしたまま身じろぎもせず、プールで水遊びをしている連中に眼をこらしていた。やがて、ふと自分がタバコに火もつけていなかったことを思い出したらしい。タバコをくわえ、両手で風除けを作って、ライターのやすりを回した。芯に火が点ると、小さいけれど安定した黄色いほのおが浮かび上がり、手でおおっているせいで、風にゆらぐこともなかった。
「こちらにも火を貸してもらえますか」私は声をかけた。
「おっと失礼。あなたがまだおつけじゃなかったのを忘れてました」
私は手を出してライターを受け取ろうとしたのだが、青年は立ち上がるとこちらまでやって来て、火をつけてくれた。
「ありがとう」私は礼を言い、青年は自分の席に戻った。
「楽しい休暇をお過ごしですか」と私は聞いてみた。
「ええ、ここはすごくいいところですね」
しばらく誰も口をきかなかった。老人のもくろみはうまくいったのだ、とんでもないことを持ちかけられた青年は、こんなにも動揺してしまっているのだから、と私は考えた。静かに座っている青年の内部に、緊張感がさざなみのようにひろがっていっているのが、手に取るように感じられた。やがて彼は椅子の上で落ち着かなげに座り直したかと思うと、胸をこすったり、首の後ろをさすったりし始め、やがて両手を膝に乗せると、膝頭を指先でトントンとたたきはじめた。じきに片方の足もそのリズムに加わる。
「言っておられる賭けとやらをもう一度確認させてください」青年はとうとう口にした。
「上のあなたの部屋で、このライターで十回連続、火をつけることができさえすれば、ぼくはキャデラックを手に入れることができるんですね。もし一回でも失敗したら、左手の小指は、切り取られてしまう。そうでしたね?」
「そういうことです。それが賭けですね。でも、あなた、怖がってるですね」
「もしぼくが失敗したらどうするつもりなんです。あなたが切り落としているあいだ、ぼくはじっと差し出してるんですか」
「とんでもないです。それは良い考え、ないです。あなた、指、引っ込めるかもしれません。私、こうするです。始めにあなたの手、テーブルにくくります、それから私、ナイフ持って立つです、ライター、つかなかったら、すぐ切り落とす」
「何年型のキャデラックなんです」青年はたずねた。
「失礼。私、わかりません」
「そのキャデラックは製造されて何年になるんですか?
「ああ、わかりました! 何歳か、あなた聞いてるですね。はい。去年できました。新しい車ですね。でも、あなた、賭けしませんよ。アメリカ人、そんなことしないね」
一瞬の間をおいて、青年はまずイギリス娘、ついでわたしのほうに視線を動かした。「やるさ」語気鋭くそういった。「賭けるよ」
「すばらしい!」小柄な老人は、一度だけ音を立てずに両手を叩いた。「まことに結構。すぐ、始めるです。それから、あなた」ここで私のほうに向き直った。「あなた、お願いです、何と言いますか、審…審判員、してください」青白いというより、ほとんど色のない虹彩の中央に、黒い点のような瞳孔が光っていた。
「私にはこんな賭けはどうかしているようにしか思えないですね。とてもじゃないが、やっていいようなことじゃない」
”
「わたしもイヤだわ」イギリス娘も言った。彼女が口を開いたのは初めてだった。「なんだかバカみたいよ、そんな賭け」
「ほんとうにこの青年の指を切るつもりなんですか、もし彼が負けたとしたら」私は聞いた。
「もちろんそうするです。それにもちろん、この人、勝ったら、キャデラック、この人のもの。さぁ行きましょう。私の部屋へ行きましょう」
老人は立ち上がった。「あなた、まず、服、着たいですか」
「いいえ」青年は答えた。「このままで行きますよ」それから私のほうを振り向いた。「レフェリーとして一緒に来てもらえませんか」
「いいですよ、行きましょう、こんな賭けをするなんて、どうかしているとは思うんだが」
「君もおいでよ」青年は娘にも声をかけた。「見に来るといい」
先頭に立つ小さな老人は、庭を抜け、ホテルの建物に入っていった。その姿は生き生きとして楽しげで、歩くときにも前よりいっそうつま先立ちになって、高く弾みながら進むのだった。
「私、別館います。あなた、車、見たいですね? ここ、あります」
老人はホテル正面の車寄せが見える位置まで私たちを引っぱっていくと、そこに立ち止まった。指さす先には、光沢のある淡い緑色のキャデラックが停まっている。
「あれ、車です。緑の車。あなた、好きですか」
「わぁ、すごい車だ」青年は言った。
「結構、結構。上、行って、車、あなたのもの、なるかどうか、やってみましょう」
私たちは後に続いて別館に入り、二階へ上がった。老人はドアの鍵を開け、私たち一行を広くて居心地の良さそうな二人用の客室に招き入れた。一方のベッドの端には女性用の部屋着が横向きに広げてある。
「まず、私たち、マーティニ、一杯、飲みます」
部屋の反対側の隅に小さなテーブルがあり、酒の用意がしてあった。シェイカー、氷、グラスもいくつもあって、カクテルを作る準備がすっかり整っている。老人はマーティニを作り始めたが、そのまえにベルを鳴らしたので、ノックの音とともに黒人のメイドが入ってきた。
「おぉ」ジンのボトルを下ろした老人はポケットから財布を取りだしてポンド札を一枚抜いた。「お願い、ありますです」そのポンド札をメイドに渡す。
「取っておくですね。いまから私たち、ここでゲーム、やりますね、それで、あなた、わたしのために、ふたつ、ちがった、三つ、もの、持ってくるです。私はくぎ、四、五本ほしいです。金槌も。ナイフ、いや、肉切り包丁、あなた、これ厨房から借りてくるです。持ってくる、できますね?」
「肉切り包丁ですか」メイドは眼をまん丸にすると、胸の前で両手を握り合わせた。「ほんとうに肉切り包丁がお入り用なんですか?」
「そう、そうです、その通り。さあ、持ってくるですね。私に、さっき言ったもの、そのとおり、見つけるです」
「わかりました。探してまいります。できるだけのことはいたしますけれど……」そういうとメイドは部屋を下がった。
小柄な老人は、ひとりずつ、マーティニを手渡していく。私たちはそこに立ったまま、口をつけた。面長な顔にそばかすが散り、とがった鼻の青年は、色あせた茶色い水着を着ているだけの裸に近い格好、骨格のしっかりした金髪のイギリス娘も水色の水着姿で、カクテルグラス越しに青年から目を離さなかった。小柄な老人は、純白のスーツに身を包んでマーティニをすすりながら、あわい色の水着を着ただけの娘を、ほとんど色のない虹彩を向けてじろじろと見ていた。いったいどうなっていくのか、私には想像もできない。老人は真剣そのもので賭けに臨んでいるようだし、それだけならいざしらず、指を切り落とすことまで、真剣そのものになっているらしい。だが、冗談抜きで、青年が失敗したらどうなる? そのときは手に入れ損ねたキャデラックにこの青年を乗せて、病院へ急行しなくちゃならないじゃないか。まったく結構な話だ。さてもこれほどすばらしいことがほかにあるんだろうか。ここまでバカらしい、無意味な話は、実際、聞いたことがないぞ。
「馬鹿げた賭けだとは思わないかい?」私は言ってみた。
「悪くない賭けだと思いますよ」そう答える青年は、すでに結構な量のマーティニを飲み干していた。
「馬鹿げてるわよ。ほんと、バッカみたいよ。もし負けちゃったらどうするのよ」
「たいしたことじゃないさ。考えてみたら、生まれてこのかた、左手の小指が何かの役にたったなんてことは一回もなかったぞ。ほら、こいつがさ」青年は小指をもう一方の手でつかんでみせた。「こいつはこれまでぼくの役に立ったことなんてなかったのさ。だからこいつを賭けたところで、いけない理由なんてないじゃないか。うん、実にいい賭けだぞ」
小柄な老人は笑みを浮かべると、シェイカーを取り上げて、ふたたび私たちのグラスを満たす。
「始める前、私、審…審判さんに、車の鍵、渡すです」ポケットからキイを取り出すと、私にあずけた。「書類、所有証、保険証、車のポケット、あるです」
黒人のメイドが戻ってきた。片方の手に小ぶりの肉切り包丁、肉屋が肉と骨を切り分けるのに使うような包丁を持ち、もう一方の手には金槌と釘が入っているらしい袋を持っている。
「すばらしですね。あなた、全部持ってきてくれました。ありがと。ありがと。もう行ってよろしです」メイドがドアを出ていくのを待ってから、老人は道具をベッドに置いていった。「これから、私たち、用意するですね。よろし?」それから青年に「手伝ってくださいね。このテーブル。私たち、チョト、運びます」
ホテルによくある書き物机で、縦90センチ、横120センチほどのシンプルな矩形、吸い取り紙やインク、ペンや紙がのせてある。老人と青年は壁際から離して部屋のなかほどに置くと、上の物をどけた。
「さて、つぎ、椅子です」老人は椅子を一脚抱えると、テーブルの脇まで持ってきた。てきぱきとした動作、生き生きした身のこなし、ちょうど子供のパーティでやるゲームの準備をしているようだ。「さて、釘、いりますですね。釘、打たなければなりません」釘を数本取ってくると、テーブルの天板に金槌で打ち込みはじめた。
私たち、青年、娘、それから私は、マーティニを持ったまま、小さな男が立ち働くのを見ていた。平らになるまで打ち込むのではない。てっぺんが少し突き出るぐらいは残しておき、15センチほどあいだをあけてもう一本テーブルに打つ。それから指で、どのくらいしっかり刺さっているかを確かめる。
このクソ野郎、これはどう見たって初めてなんかじゃないぞ。私は胸の内でそう言った。いささかのためらいもない。テーブル、釘、金槌、肉切り包丁。自分に必要なものも、どのように段取りをつけていくかも、たなごころを指すがごとく、よくわかっているのだ。
「さて、つぎです」男は言った。「あと、必要なもの、紐だけです」紐を見つけてくると続けた。「結構、結構。準備できましたね。あなた、ここに座るです」と青年に言う。
青年はグラスを置いて、腰を下ろした。
「左手、釘のあいだに置くです。釘、あなたの手、正しい位置にするため。結構、いいですよ。私、あなたの手、ゆわえるです。テーブルに固定します」
男は紐を青年の手首にかけてから、ての甲の一番広い部分に数回巻き付けると、釘に固く結びつけた。その手際は見事なもので、終わってしまえば、青年がどんなに手を引き抜こうとしたところで、まったく無駄に終わるだろう。動かせるのは指だけだ。
「さて、あなた、小指だけ残して、残り、しっかり握るです。小指、伸ばして、テーブルにつける。すばらしい! すばらしい! さあ、始めるです。あなた、右手、ライターつけます。でも、チョト待て」
男はベッドに駆け寄ると、肉切り包丁を取り上げた。戻ってくると、肉切り包丁を持ったままテーブルの傍らに立った。
「みなさん、いいですね? 審判さん、開始、宣言してください」
イギリス娘は薄い水色の水着姿のまま、青年の椅子のすぐうしろに立っている。ただそこにいるだけ、声をかけるでもなかった。青年も静かに腰を下ろし、右手にライターをにぎったまま、じっと肉切り包丁に眼をやっていた。小さな男は私から目を離さない。
「始めていいかね」私は青年にたずねた。
「いいですよ」
「あなたは?」小さな男にも聞いてみた。
「準備、オーケーですよ」そういうと、肉切り包丁を宙にふりあげ、青年の小指の真上50センチのところで留めるといつでも切り落とすことができるように待ちかまえた。青年はそれをじっと見てはいたけれど、ひるむようすもなく、唇が動く気配もない。いったんあがった眉が、かすかにしかめられただけだった。
「いいでしょう」私はいった。「始めてください」
「ぼくがつけた回数を、声に出してカウントしてもらえませんか」
「わかったよ。そうしよう」
親指でライターのふたを押し上げ、その指をこんどはやすりの部分にのせて、いきおいよく引く。ライターの石は火花を散らし、芯に火がともったかと思うと、小さな黄色い炎があがった。
「一回!」私がコールする。
青年は吹き消さずにふたをかぶせると、そのまま五秒ほど待って、ふたたび開けた。
やすりを強くこすると、ふたたび芯から小さな炎が立ち上った。
「二回!」
ほかに声を出す者はいなかった。青年はじっとライターを見据えたままだ。小さな男も肉切り包丁をかまえたまま、ライターから片時も眼を離さない。
「三回!」
「四回!」
「五回!」
「六回!」
「七回!」確かにこのライターはよくできたものにちがいなかった。シュッとこすると大きな火花が飛ぶし、芯の長さもちょうどいい。私は青年の親指が、ふたのてっぺんにかかって、カチンと炎の上にかぶさるのを見た。しばらく間があく。それから親指がふたたびふたを持ち上げた。すべてが親指だけの動作である。親指がなんでもやってのけている。私は息を吸いこんで、八回、というのに備えた。親指がやすりをこする。火花が散る。ぼっ、と小さな炎があがる。
「八回!」私がコールしたそのとき、ドアの開く音が聞こえた。みながいっせいにふりかえった先には、扉を背に女が立っていた。小柄で黒髪、初老の女性は、そこに二秒ほど立ちつくしたあと、大声でわめきながら部屋のなかにものすごい勢いで入ってきた。「カルロス! カルロス!」男の手首をつかまえると、肉切り包丁をもぎ取ってベッドに投げ捨てる。小柄な男の白いスーツの襟の折り返しを両手でつかみ、はげしくゆさぶりながら鋭い語調で早口にまくしたてるのだが、その言葉はスペイン語のようだ。女があまり激しくゆさぶるので、男の姿がはっきりしない。おぼろげに、霞のように、その輪郭だけがガクガクと揺れている。ちょうど回転する車輪のスポークを見ているようだった。
やがて女の動きが鈍くなると、小男の姿はまたはっきりとしてきた。女は老人を部屋の向こうまで引きずっていくと、ベッドに押しつけた。端にちょこんと腰をのせた男の方は、眼をパチパチさせながら、首が回るかどうか、頭を動かして確かめている。
「申しわけございません」と女が言った。「こんなことをしてしまってほんとうにごめんなさい」その英語は、ほとんど文句のつけようがない。
「あまりにひどいことです。ほんとうにわたしがうかつでした。ほんの十分、夫をひとりにしてしまったのです。髪を洗いにいって、戻ってきたら、また悪い癖をだしてしまって」
青年は自分の手をテーブルに縛りつけている紐をほどいた。イギリス娘とわたしは言葉もなく立ちつくしている。
「ほんとうにこまった人です。わたしたちが暮らしていたのは南方の国だったのですが、そこで夫は指を四十七本、四十七人の人から取り上げたのです。かわりに車も十一台、失いましたが。そのあげく、収監するぞと脅されました。だからわたしがここへ連れてきたのです」
「私たち、チョト、賭け、しただけね」小男はベッドにすわったまま、不平がましく言った。
「あのひとは車を賭けたんでしょう」女が言った。
「そうです」青年が答えた。「キャデラックを」
「車なんて、あのひとは持っていませんのよ。あれはわたしのものなんです。だからいっそうひどいことですわね。賭けるものを何も持っていないのに、あなたと賭けをするなんて。ほんとうに恥ずかしいことですし、何もかも申し訳なく思っています」この女性はなかなかしっかりした女性のようだった。
「さて」私は口を挟んだ。「あなたの車のキイです」そう言って鍵をテーブルに置く。
「チョト、賭けただけね」小男はまだぶつぶつ言っていた。
「あのひとはもう賭けられるようなものは何も持っていないのです。ほんとうになにひとつ、持っていないのですから。どんなちっぽけなものだって。実をいうと、わたしが勝って、なにもかもあのひとから取り上げたのです、ずいぶん長い時間をかけて。ええ、時間がかかりました。それはそれは長い時間が。つらい務めでした。けれど、わたしはとうとう全部取り上げたのです」青年を見上げた女の顔には笑みが浮かんでいた。どこか鈍い色合いの、悲しげな笑みだった。女はこちらにやってくると、テーブルからキイを取ろうとして、片手を伸ばした。
いまでもその手が目の前に浮かんでくる。たった一本の指と、親指しか残っていない女の手が。
The End
アカウントを作成 して、もっと沢山の記事を読みませんか?
この記事が気に入ったら Kohr さんを応援しませんか?
メッセージを添えてチップを送ることができます。


この記事にコメントをしてみませんか?